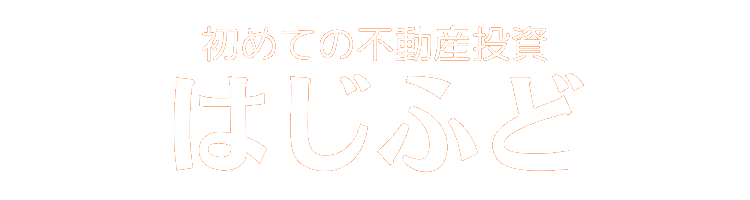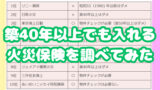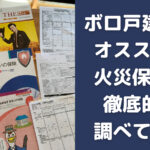こんにちは。不動産投資をしている藤本紗帆です。
大家でも築古木造の物件は火災保険や地震保険に入らないという人もいるようです。
特に火災保険と比べて地震保険は加入率が低いです。
大家が地震保険に入らないのはアリなのか?考察してみます。
付帯率は69%、加入率は34.6%
地震保険の加入率は、損害保険料率算出機構が発表しています。
火災保険とセットで地震保険をつけている割合(付帯率)都道府県別の地震保険世帯加入率は69%、全体の加入率は34.6%です。
そもそも火災保険にも加入していない人が多いことがわかります。
(地震保険は、単独で契約することはできず、必ず火災保険とセットで契約します。)
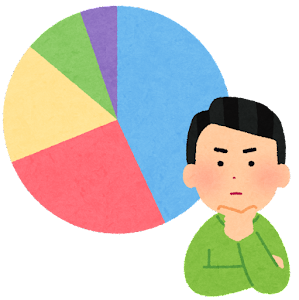
加入率が高いのは宮城県、熊本県
都道府県別で見ると、宮城県の加入率(51.9%)が一番高く、次に熊本県(43.5%)となっています。
やはり、震災を経験した地域は他の地域と比べて高い値となっています。
活断層が多い、南海トラフの地震で被害にあう可能性がある地域などはやはり加入したほうが安心な気もします。

警戒地域になると新規契約できない
火災保険の契約時に地震保険を契約しなかった場合でも、火災保険の保険期間の途中から地震保険をかけられます。
ただし、警戒宣言が発令されたときは、その地域では地震保険の新規契約、中途付帯、増額契約はできません。
大きな地震が来るかも!となってから契約することはできないわけです。

地震による火災は地震保険でないとダメ
火災保険だけ加入する人もいますが、地震による火災は火災保険では補償されません。
地震に強い建物と地盤であれば地震保険に入らなくてもよさそうですが、地震による火災は怖いですね・・・。
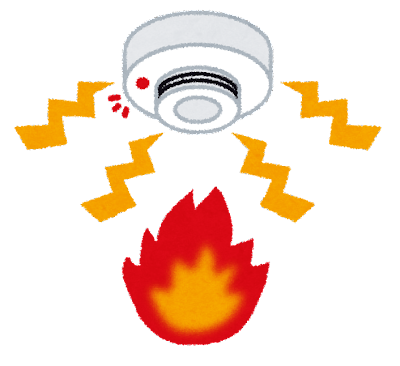
地震保険はどの保険会社でも同じ
火災保険は保険会社によって契約の内容や補償額もさまざまです。
対して、地震保険は民間の保険会社と政府が共同で行う公益性の高い保険です。
そのため、保険料に保険会社の利潤は含まれず、どこの保険会社で契約をしても一律の保険料額となっています。
地域や構造によって保険料が変わる
地震保険の保険料は、エリアと建物の構造によって違いがあります。
エリアによって異なるのは、地震調査研究推進本部によって、活断層や地盤の固さが勘案して算出されているためです。
構造による違いは、ざっくりと鉄筋コンクリート(RC)造や鉄骨造は安く、木造は高くなります。
ただし、基礎と建物がいくら頑丈でも、水道の配管が破裂したり、建物自体が傾いてしまうこともあります。
つまり、RCだから頑丈で安心というわけではありません。
建物が残ったとしても、津波で室内がドロドロになって鉄部がさびてしまったら結局建て替えなければいけません。
RCや鉄骨造の場合、撤去費用は木造とは比べものにならないコストがかかります。

地震保険の保険金と判定
地震保険の保険金額は、セットした火災保険の保険金額の50%が上限で、火災保険のように建物を建て直す費用までは出ません。
保険金の上限は建物は5000万円までと決まっています。

地震被害の判定
地震被害の判定は火災保険とは違い、保険会社は対象物件の調査をします。
この調査で、「地震で損害を受けた」と判定されることが必要になります。
地震保険の損害区分は以下のようになっています。
| 損害の程度 | 支払われる保険金額 |
| 全損 | 建物の地震保険金額の100% |
| 大半損 | 同60% |
| 小半損 | 同30% |
| 一部損 | 同5% |
地震で損害を受けても、「一部損」にも該当しない場合、保険金は支払われません。
大地震が発生した場合でも短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払う必要があるためです。
なお、主要構造部の損傷に関しては認定されますが、塀やフェンス、門などの外構部は認定されません。
家の外のブロック塀とフェンスが倒れたという場合は対象外です。
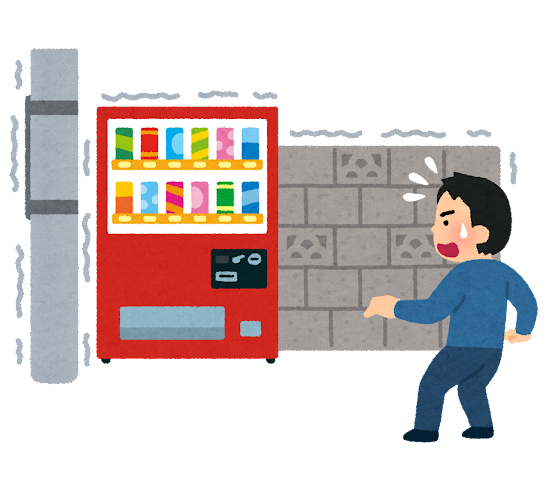
高額な払戻しを受けるものではない
東日本大震災のときには、東京近郊では9割が一部損認定で、ほとんどの人は評価額の5%、つまり100万円程度の支払いしか受けていません。
また、ある大手保険会社の資料によれば、宮城県ですら、支払いナシ10%、一部損75%、半損15%程度の割合で、全損と認定されたのは1%以下です。
ちなみに不動産ファンドでは、地震保険はコストが高いと考えられており、加入していない物件のほうが圧倒的に多いようです。
保険金額の設定に一工夫
X(旧Twitter)で見たのですが、保険金額の設定に工夫をしている投資家もいました。
- 融資額だけ保険金額を設定する。現金購入の場合は入らない。
- 「借入残高ー路線価=保険金額」にする。
保険会社が設定する再調達価格は高いので、自分で調整して保険料を安くしているということです。
まとめ
近年は地震被害が増えているために、保険料の値上げが続いています。
特に津波の心配があるような場所では加入すべきだと思います。
ただ、地震保険に入れば安全というわけではなく、どの程度の損害が発生した際にいくら払い戻しを受けられるかを試算して、保険料が安いか高いかを判断すべきです。
築古物件の火災保険はこちらの記事でも解説しています。▼
読んでいただきありがとうございました。